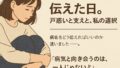はじめに
病気とともに生きる中で、制度の存在が心の支えになることもあります。
家族性大腸ポリポーシスは〝指定難病〟ではありません。この点について、当事者にとっては不満の声を発する方が多いのではないかと思います。私もその一人です。
いずれか、〝指定難病〟に入ることを願ってはおりますが、そんな中でも使える制度はあるので、私の知る限りで紹介させていただきます。
医療費に関する制度
入院・手術・退院・通院などにかかる医療費を助けてくれる制度をご紹介します。
医療費控除
1年間の医療費が10万円(または総所得の5%)を超えた場合に、税金の一部が戻ってくる制度です。
入院費・手術費・通院費だけではなく、交通費や薬代も対象になります。
ストーマ装具の購入費も医療費控除の対象となります。(※医師の指示が必要となる場合があります)
高額療養費制度
1ヶ月(1日から月末まで)の医療費の自己負担限度額(所得によって決まる)を超えた場合、超過分が返還される制度です。
例えば入院や手術などで一時的に大きな医療費が発生しても、あとから一部戻ってくることで経済的な負担を減らすことができます。
〝1医療機関ごと〟に計算されるため注意してください。複数医療機関との合算はできませんのでご注意ください。
限定額適用認定証
事前に申請することで、窓口で支払う医療費があらかじめ限度額(所得によって決まる)までに抑えられる制度です。
この制度を使わなければ、〝一旦全額払って、後から戻ってくる〟という負担が不要になります。
高額療養費と一緒に覚えておくとよいでしょう。
因みにマイナ保険証の移行で、手続きせずとも限度額以上は支払わずにすむ医療機関も増えてきております。一部医療機関では対象となっていないので事前に確認するとよいでしょう。
高額療養費の世帯合算
家族がそれぞれ医療費を支払っていても、同じ健康保険に加入している家族の医療費も合算できる仕組みです。
たとえば、本人と子供が別々の医療機関で支払いが生じても、限度額(所得によって決まる)を超えた分が戻ってくることがあります。
なお、世帯合算の対象となるのは、個別に21000円以上の自己負担がある場合に限られます(一部例外あり)。
公的制度以外のサポート:任意の医療保険
家族性大腸ポリポーシスは、進行によって長期通院や複数回の手術が必要になることがあります。
公的制度だけではまかないきれない部分を補う手段として、任意の医療保険やがん保険などの民間保険に加入している方もいます。
ただし、既に病気がわかってからでは加入が難しい・制限がつくことがほとんどです。
そのため、今現在「家族に発症者がいる」「遺伝性の疾患があると診断されている」などの段階で、将来を見据えて準備することが大切です。
加入可能かどうかは保険会社や商品の種類によって異なるため、事前に「告知義務」や「加入条件」をよく確認しておきましょう。
生活費に関する支援
現役世代だけど、仕事ができなくて収入がないといった、生活費に関する制度を紹介します。
失業給付金(雇用保険)
退職後、働けない状態でも一定期間は生活費の支援が受けられる制度です。
ただし〝自己都合退職〟か〝会社都合退職〟か〝病気による退職〟かで受給条件や給付開始時期がかわります。
また退職理由や年齢、被保険者期間などによって〝所定給付日数〟と〝支給額〟が変わります。
それぞれによって受給期間も変わります。下記の通りです。
自己都合の場合:90日〜150日
会社都合の場合:90日〜330日
病 気 の 場 合:働ける状態になってから90〜150日(※状況によっては延長あり)
医師の診断書で『就労困難』と判断された場合、受給期間の延長申請ができるケースもあります。
働ける状態になるまでは傷病手当金を受給、働ける状態になったら失業給付金に切り替えるとよいでしょう。
傷病手当金(健康保険)
病気やケガで働けなくなったときに、給与の2/3相当額が支給される制度です。
支給される期間は、最長で1年6ヶ月間。連続して会社を休んでいる間だけでなく、復職と休職を繰り返す場合も通算でカウントされます。
条件としては、以下のすべてを満たす必要があります。
・業務外の病気やケガによる療養
・仕事に就けないこと
・連続して3日以上休み(待機期間)
・休んでいる間に給与ねの支払いがない、または一部だけ
家計の大きな支えになる制度なので、働けない状態が続く場合は早めに申請を検討しましょう。
障害基礎年金(国民年金加入者が対象)・障害厚生年金(厚生年金加入者が対象)
障害年金は、病気やケガなどで生活や仕事に支障をきたすようになったときに支給される年金です。
公的年金制度の一部で、障害の程度や加入していた年金の種類に応じて「障害基礎年金」または「障害厚生年金」が支給されます。
等級は1級・2級(厚生年金の場合は3級も)に分かれ、支給額や条件が異なります。初診日・納付要件・障害認定日が重要なポイントになります。
ストーマ生活している人向けの制度
ストーマの方は2〜3日に1回の頻度で装具を変える必要があり費用がかさみます。助成に関する制度を紹介します。
日常生活用具給付制度
ストーマ装具の費用を自治体が一部または全額負担してくれる制度です。
申請には身体障害者手帳が4級以上必要となる場合があります。
また装具の種類によって上限額が決まるため、毎月の負担がゼロになるとは限りません。
その他知っておきたい制度・支援
障害者手帳の取得について
大腸全摘出やストーマの方は『排泄機能障害』として手帳が交付されることがあります。
取得することで、医療費・装具費用の助成・税控除、交通機関の割引などの対象になります。
介護保険制度について
40歳以上でストーマを含む介護が必要な状態にある場合、在宅介護や福祉用具レンタルなどの支援が受けられます。
保育園の継続利用について
子育て中で手術や療育中のために働けなくなった場合でも、一時的に保育園を継続して利用できる猶予制度があります。
ヘルプマークについて
ストーマ装具をつけているとき、服に隠れて外観では他の方と変わりありません。
通勤や外出時に周囲への気づきやすさにつながります。
思いやり駐車場について
各自治体の基準により、対象となる可能性があります。
便の処理やその他トラブルに急いでトイレを使用する必要があるなど、移動制限を理由に配慮が得られることもあります。
おわりに
「指定難病ではない」という壁に、最初は私も落胆しました。
でも調べてみると、申請すれば活用できる制度は思ったよりもたくさんありました。
誰も教えてくれないからこそ、自分で情報を探すことは本当に大事だと感じます。
〝制度は知らないと使えない〟ことが多いからこそ、まずは知ることが一歩になります。
この記事が、同じ境遇の方に少しでも安心材料となれば嬉しいです。